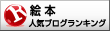壮大な生命のドラマ
舞台仕立てで、地球上に生命が生まれたときから、今までのお話をつづった絵本です。

読み聞かせ目安 高学年 ひとり読み向け
あらすじ
舞台仕立てで、地球上に生命が生まれたときから、今までのお話をつづった絵本です。
プロローグからエピローグ、全5幕で構成されています。
プロローグ
わたしたちの銀河系から太陽系、地球と月。火成岩から変成岩、堆積岩の生成までのお話。
1幕 古生代
カンブリア紀からオルドビス紀の海の生き物、シルル紀の海辺の生き物、デボン紀の海辺の生き物、石炭紀の沼地の生き物、ペルム紀の砂漠の生き物のお話。
2幕 中生代
三畳紀の川の生き物からジュラ紀の沼地の生き物、白亜紀の海と陸の生き物、平原の生き物のお話。
3幕 新生代
暁新世・始新世の森の生き物、漸新世の低地の生き物、中新世の平原の生き物、鮮新世の生き物、氷河時代の生き物のお話。
4幕 にんげんの時代
有史以前の人間から、有史後の人間。アメリカ初期の移民の人たち、農業が盛ん
だったころの生活、農場を捨てていく人たちのお話。
5幕 現代のひとびとの生活
春夏秋冬、早春の営み。ある春の朝、その日の午後、夜、新しい日の夜明けまでのお話。
エピローグ
主人公はあなた。あなたのお話のはじまりです。

読んでみて…
地球上に生命が生まれたときから今までの壮大なお話を、面白い舞台仕立てで描いた絵本です。
表紙を開くと、そこは劇場。臙脂のベルベットのカーテンが掛かった舞台の前に、観客がつぎつぎと席についていく様子が描かれています。
お芝居が始まる前の劇場の、緊張感とワクワク感が伝わってくる絵です。
ページをめくると、赤いリボンで綴じられた「せいめいのれきし」と書かれたプログラム。その次のページは、プログラムの目次です。
ナレーターは、天文学者、地質学者、古生物学者、歴史家、おばあさんとバージニア・リー・バートン(この絵本の作者)です。
主役の動物や植物たちも紹介されています。
本当のお芝居のプログラムのような、芸の細かい演出で、舞台に対するワクワク感がさらにつのります。
そしていよいよ幕が上がり、プロローグ。
幕の後ろのスクリーンには、広大な宇宙が映しだされ、ナレーターの天文学者が望遠鏡を画面の指示灯にしながら、お話のはじまりです。
お話は、銀河系、太陽の誕生のから、太陽系、わたしたちの地球へと順に焦点が絞られていきます。
このプロローグの場面は、まるでプラネタリウムを見ているよう!
広大な宇宙の誕生、広がり、きらめきをとても美しく見せてくれます。
それからナレーターは天文学者から地質学者にかわり、焦点化は場を追うごとに進んでいき、地球上での火成岩、変成岩、堆積岩の生成、生物が誕生する舞台の準備が整っていく過程を、わかりやすく見せてくれます。
この絵本は、全編とおして右側のページに舞台が描かれ、左側のページにそれぞれの細かい説明が、絵とテクストで示されているのですが、左側の説明ページは、細かいだけでなく、それぞれ地質の形成過程や、生物の発生、進化の過程などを順を追って、丁寧に時の流れが伝わるようにも描かれています。
わかりやすく面白く、生命の誕生の過程を追うことで、私たちの知識も順を追って積み重なっていくような感じになっているのです。
そしていよいよ第1幕。
地球上に生命の誕生する本編がはじまります。
ナレーターは古生物学者。カンブリア紀からペルム紀までの、古生代の生き物の誕生のお話です。
幕が開くとプロローグでは、平面のスクリーンだった舞台が、いつの間にか奥行きと立体感のある舞台装置にかわっています。
輝く朝日が地平線からのぼり、緑が萌えています。
太陽に照らされ輝く水面。水中にはさまざまな藻類が生え、さまざまな生きものが泳いでいます。
透き通った空気と水のきらめきがとても印象的です。
明るく輝く第1幕ですが、6場になると地球の気候はかわき、火山活動が活発になって太陽が隠れ寒くなり、たくさん現れた生き物たちも死滅していき、静かに幕が降りていきます。
次にカーテンが開くと第2幕。中生代のお話です。
爬虫類の仲間の恐竜と、原始的な哺乳類の時代のはじまりです。
たくさんの恐竜が出てくるので、子どもたちにはもっとも喜ばれる場面です。
舞台では、おおきなアパトサウルスが、長い首を舞台から飛び出すほど伸ばし、口にくわえた植物から水を滴らせています。画面を突き破って出てきそうなほどの大迫力です!横にいるナレーターの古生物学者と比べると、その大きさに驚きます。
でも、白亜紀も最後になると、また気候は寒くなり、小天体の衝突のあと、恐竜たちは鳥類に進化したもののほかは死滅し、この舞台の恐竜たちも、卵を抱えて舞台の袖に退場です。
場面はまたかわり第3幕。新生代のお話になり、熱帯樹の生い茂る森が登場します。
まぶしい木漏れ日が舞台を金色に照らし、蒸し暑い空気感が舞台からただよってくるようです。
緑の木々、色鮮やかな花々が咲き、爬虫類、両生類、鳥類、哺乳類、さまざまな動物たちが登場します。
私たち人間の仲間、哺乳類は第3幕の各場で登場してくるものそれぞれが、舞台端に立つナレーターに、舞台から飛び出してやってきては握手をしています。人間に近い生き物であることがよく伝わってきます。
でもまた、地球は寒くなり、氷河時代。それまでの動物たちは、舞台の袖に去っていき、幕が降りていきます。
そして第4幕。第3幕の終わりにやっと登場した人間が、表舞台に立つ時代のはじまりです。
洞穴の中で火を灯し、壁に絵を描く人間。洞穴の向こうには、山河か広がり、動物たちが歩いています。
次のページ、2場では舞台の端に歴史家がナレーターとして登場。
大きな机に座り、本を山のように積んで、エジプト時代からギリシア、ローマ、中世、ルネサンス、大航海時代をいっきに語り、舞台はアメリカ。インディアンがカヌーで川下りをしています。
そして3場。アメリカ開拓時代。イギリスから移住した開拓者たちの暮らしが描かれ、4場になるとナレーターは、歴史家からおばあさんに。
あれ地を耕し耕作地にし、さまざまな作物を実らせ、家畜を飼い、農家が繁栄していくさまが表されます。
でも、5場になると農場には売地の立て札。
何代かたって、人々は西武の開拓地や都会に移っていってしまったのです。
そして第5幕。舞台は広大な大地から、1か所に焦点化され、「わたしたち」が古い果樹園と草地と森を買い、ちいさな家を移して暮らすという場面になります。
ナレーターはおばあさんから作者のバージニア・リー・バートンへ。
「ちいさな家」を移すというと、同じくリー・バートンの『ちいさいおうち』を思い起させます。
「わたしたち」は、ここで草木を整え、羊を飼い、子を育てます。
左ページには、この家族のアルバムが、年を追って写真の数を増していくさまが描かれます。
場面の焦点化はさらに進み、春夏秋冬の人々の営み、めぐりめぐる日々の暮らしが表されます。ナレーターのリー・バートンも、いつの間にか舞台の中の人となり、雪かきしたり、絵を描いたりしています。
そしてさらに焦点化は進み、きのう、今日の夜明け。春のある1日。
そして第5幕は終わり、エピローグ。新しい1日のはじまり。太陽がのぼり、「あなた」が主人公のお話がはじまるということに。
明るい太陽が、窓いっぱいに輝き、その窓辺には今この一瞬を指し示す目覚まし時計が置いてあるというところで、このお話は幕を閉じる・・・というか、窓に掛けられたカーテンが(これまでの舞台のカーテンと同じ臙脂のカーテンです)開いていくというかたちになって、見ているわたしたちに、どうぞお話をつないでいってください、と投げかける終わり方になっているのです。
最後の目覚まし時計へつながる時の流れは、その前の場面、またその前の場面の時計からつながっていて、さらにはテクストで、
「新月がしずんでいったあと、あたりはくらくなりました。ひとつひとつ、星が、かがやきはじめました。何兆キロもとおくはなれた、何億、何十億という星のむれです。」
と語ることで、この絵本のプロローグで示した銀河のはじまりを思いおこさせ、そこから現在がつながっているということを、実感することができるようにもなっています。
実にたくみで詩的な構成です。
はるか遠い昔から続いてきた生命の営みが、今のわたしたちに続いている。今の1分1秒に続いているということを、実感させます。
最後の窓の太陽は、最初の銀河に生まれた太陽。地球上にはじめて生命が生まれたとき、地平線からのぼってきていたあの太陽と同じものだ、ということも気づかせてくれます。
長い長い、あまりにもながい生命の歴史からみると、わたしたち人間の歴史なんて、ほんのつい最近はじまったばかりのこと。今現在、世界中が新型コロナウイルスを前に、右往左往していますが、これも長い生命の歴史を思うとほんの一瞬のことだと感じられます。
でも、長い長い生命の尊い営みの積み重ねの一瞬だからこそ、わたしたちひとりひとりの生命が尊く、大事にひとつひとつの問題に対処していかなければならないんだなとも思わされます。
この絵本は、壮大なスケールで、生命の歴史を、命の営みを、子どもたちに面白く楽しみながら教えてくれる、とても優れた絵本だと思います。
書かれてある内容は、どれもみな子どもにとって専門的で難しいことです。
でも、お話を舞台仕立てにし、楽しくワクワクする演出たっぷりに描きあげ、自然科学的なことがらが苦手な子どもにも、抵抗なく受け入れられるようになっています。
作者のバージニア・リー・バートンはこの絵本を、博物館に通いつめ、8年かかって描き上げたのだそうです。
絵本ではありますが、科学的根拠に忠実に描かれています。
でも、この絵本がアメリカで出版されたのは1962年。それから50年以上の歳月がすぎ、この間、科学はめざましい発展をとげ、50年前にはわからなかったことがわかり、あやふやだったことがはっきりしてきたりして、科学的根拠に忠実だったこの絵本の内容も、古くなってしまったところがでてきました。
そこで、アメリカでは2009年、日本では2015年に、科学者の監修のもと新たな知識にもとづいた改訂版がだされました。
改訂版と旧版を並べて見てみると、ずいぶん違いがあります。
時代区分の何年前とか、星の大きさとかいった数字的なことをはじめ、動植物の名称が改められていたり、旧版には太陽系の惑星としてのっていた冥王星が、改訂版ではなくなっていたりします。中生代前期白亜紀にいたプレシオサウルスも、改訂版ではいなくなっています。
テクストの表記自体も、科学的により厳密なものに改められています。
本来、作者の没後、その著作が大きく書き直されたり、ましてやあったはずの絵を外して出版されるなんていうことはありえないことです。
でもこの絵本は、作者が科学的事実を子どもたちに正確に伝えたいという目的で描かれたもの。その遺志を守るために、大胆に改定が行われたということで、これもまた作者と科学に忠実、誠実な行為といえるでしょう。
でも、ちょっと残念なことに、テクストもより科学的に厳密な表記に改められたため、旧版が持っていた文学的、物語的な色合いが薄れてしまっているところもあります。
たとえば3幕2場で、
「いろいろな種類のほにゅう類が、さまざまな生きかたをこころみていました。」
とあるところが、
「いろいろな種類のほにゅう類が、さまざまにかたちをかえながら、進化していきました。」
というように。
文学よりの人間としては、ちょっとさみしい気もしますが、厳密に科学的にぶれのない表記となると、こうなってしまうのも仕方がないのかなと思います。
でも、楽しさ美しさ、子どもを惹きつけてやまない面白さは、改定後も変わりません。
私が読み聞かせをしている小学校では、この絵本の改訂版に、
「この本は改訂版です。○○小学校の図書室には、古い版のものもあります。興味のあるひとは、違いをくらべてみましょう。」
とメッセージをつけて、この絵本の新旧2冊を蔵書しています。
小学校の図書室では、ふつう本を新しく購入し直したら、副本として蔵書する目的のあるもの以外、古いものは廃棄しますが、この『せいめいのれきし』は、特別!
旧版のよさもあるので、ぜひ両方見てもらいたいと思い、新旧2冊蔵書しています。
『せいめいのれきし』、生命の尊く長い歴史を、誠実に忠実に格調高く伝えてくれるとても素晴らしい絵本です。
世の中が、生命の危機を感じて過ごしている今、改めて読んでみるのもいいのではないかなと思いました。

今回ご紹介した絵本は『せいめいのれきし』
1964.12.15(初版) 2015.7.22(改訂版) 岩波書店 でした。
| せいめいのれきし |
||||
|
ランキングに参加しています。ポチっとしていただけると嬉しいです。
いつもありがとうございます。